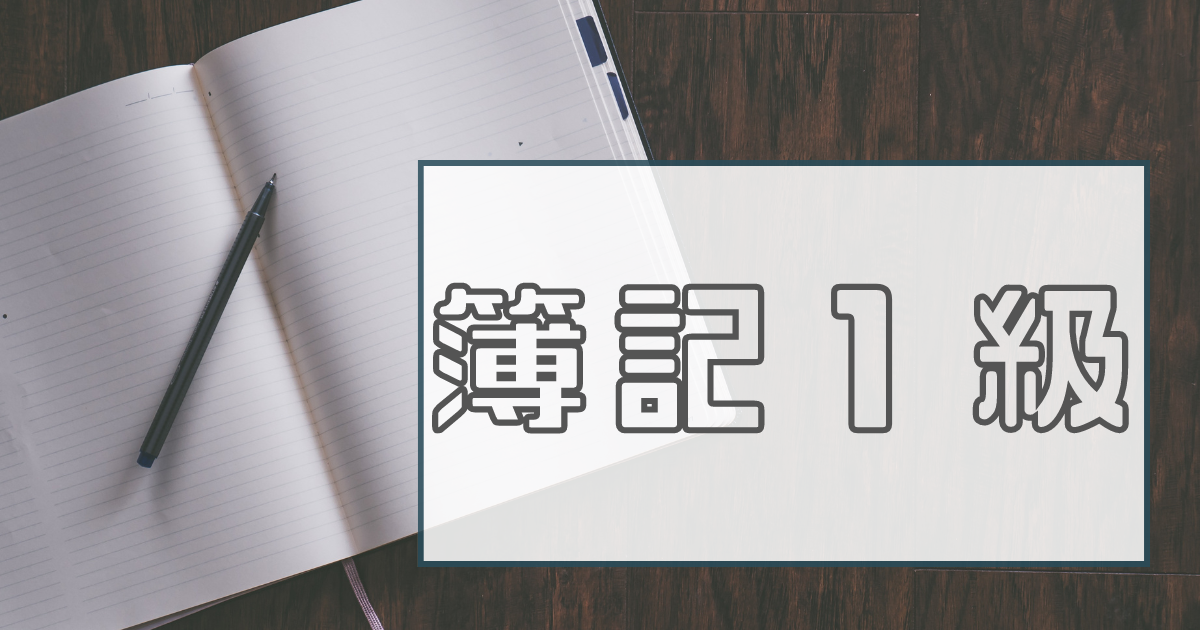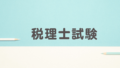1回目(第165回)受験時までの勉強方法
まず、簿記1級を受験しようと思ったときに最初に始めたのは簿記2級の復習でした。
簿記2級受験時に使用していたテキストは下記のスッキリわかるシリーズだったのですが、値段が一番安いし、ギリギリでも良いから受かればヨシ!という感覚からの選択でした。
そこで、簿記1級を受けようとまだ思っていなかったときにもう少し詳細に簿記の知識を定着させたほうが良いと考え、みんなが欲しかったシリーズの教科書のみを買っていました。
2023年8月下旬から簿記2級の教科書の商業を4周、工業は得意(だと思っていた)ので2周してから、2023年9月上旬より1級の勉強に入りました。
今までも独学で勉強をしてきたので、今回もと思い、簿記の教科書と問題集をそれぞれ商簿・会計6冊、工簿・原計6冊の計12冊を購入しました。
この後、簿記1級の範囲の広さに愕然としつつ、週10~20時間程度の勉強ペースでのんびり取り組んでいたため、結局教科書のみしか読み込むことができませんでした。
また、工業簿記の方が取り掛かりやすそうという理由から工・原から勉強を開始したため、苦手である商・会に割く時間が少なくなるというとんでもないミスを犯します。
商業簿記のテキストに手を付けたのは10月中旬という状態でした…。
結局工業簿記を3周、商業簿記はテキスト2冊目までは3周、3冊目は2周し、あまりにも理解が出来ていないため、問題が全然解けないことに絶望し、最後の1週間であわててノートにわからない論点をまとめ始めるという残念な状態になっていました。
もちろん、本番試験の商・会はボロボロでしたが、工・原はそこそこ取れていたのでうれしかった記憶はあります。
ま、たまたま簡単な問題かつ好きな問題が出ただけですけどね。
2回目(第167回)受験時までの勉強方法
2回目受験に向けて勉強を再開したのは、2024年1月からでした。
あまりにも論点の理解がボロボロだったことを反省し、なんと無料で簿記1級の動画講義を提供してくれているCPAラーニングに登録し、簿記1級の講義を見ることにしました。
登川先生、植田先生、本当にありがとうございました。
先生方のおかげで、独学テキストに比べてかなり理解が深まりました。
それぞれの先生方も個性が全く異なっていて非常に楽しく講義を拝聴することが出来ました。
その後はまた以前購入した簿記の教科書を商・会7周、工・原4周解きました。
その時点で実はもう、6月の上旬であり、問題集については商業簿記のみ2周して時間切れでした。
はい、そうです。今回も買ってあった問題集は解き切れませんでした。
そして、付属の模擬試験も1回分もできませんでした。
そして、自己採点結果は1回目受験時の点数より1点低い状態でした。
しかし、間違いなく前回よりは知識が定着しており、手が動かせている気はしました。
3回目受験に向けて
次回は問題集まで解き切って、持っている参考書をフル活用して本番に臨みます。
何なら、直前問題集を買い足して解きたいと思っています。
スケジュールきちんと立てて、今度こそ、自信をもって本番に挑戦したいです。
ちなみに、別の記事で書いていますが、8月の税理士試験に向けてスタディングの税理士講座の簿財を受講開始しました。
やはり内容が簿記1級に重複する箇所が多く、これは簿記1級受験についても理解の底上げになると思います。
8月までは税理士試験の勉強、その後11月までの約3か月となりますが、再度簿記1級に切り替えて、合格し、来年の税理士試験では税務科目の受験資格を得たいです。
にほんブログ村